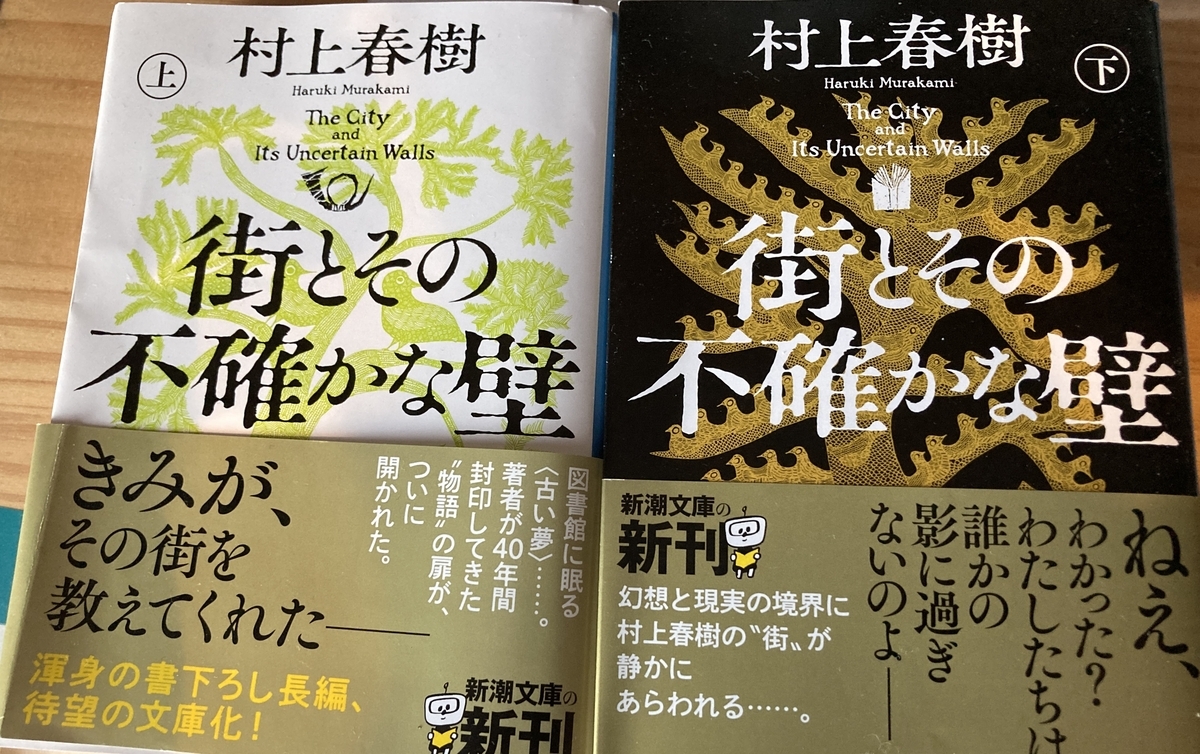『カフネ』を購入した時に「あ、村上春樹の新刊もある!」ということで。とりあえず上巻を購入しました。
『カフネ』を読み終えてから読み始めました。読み始めて、二つの世界を行ったり来たりする展開、どちらが本当の世界なのか考えて読み進めていく感覚はもう、15年くらい前に読んだ『世界の終わりとハードボイルドワンダーランド』を思い出しながら読み進めました。
ganju39.hatenablog.com
金色の獣等や石造りの街並・・・・。
上巻は大きなストーリーの展開はないのですが、丁寧に読んでいかないと物語の終わりに向けての伏線がたくさん張り巡らさせているので、じっくり読みました。
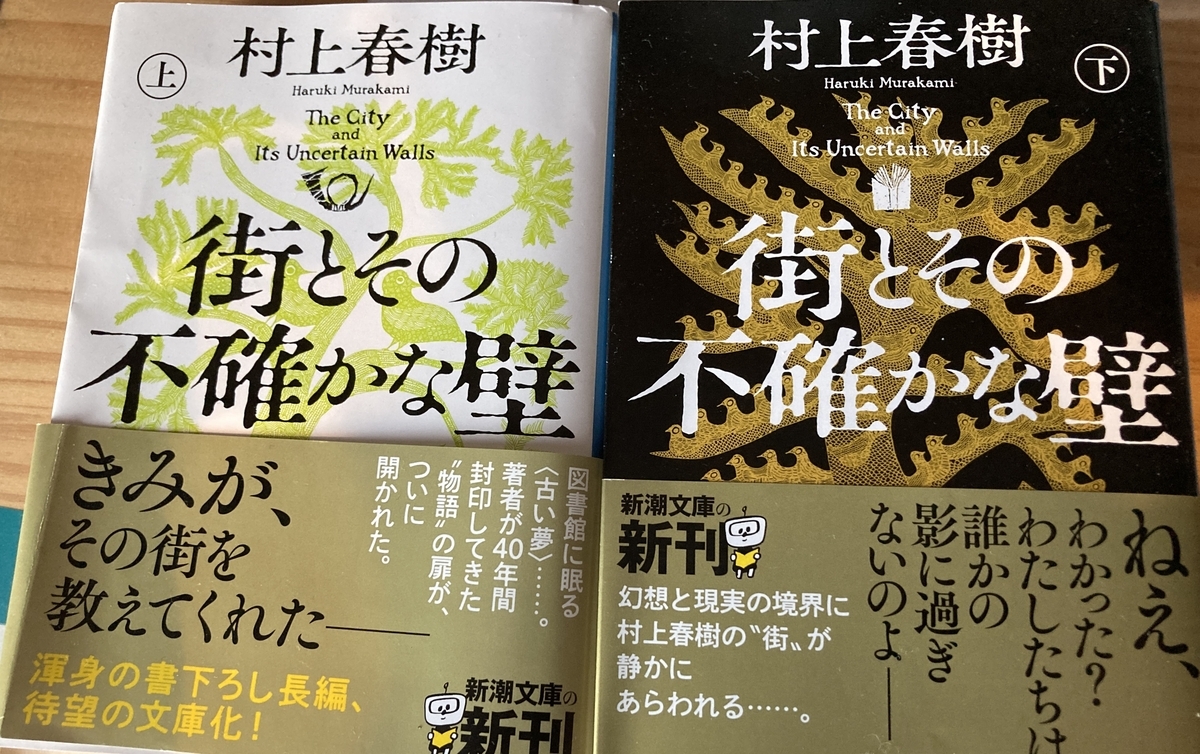
著者は1980年に中編小説「街と、その不確かな壁」、1985年に壮大な長編小説『世界の終りとハードボイルド・ワンダーランド』(谷崎潤一郎賞受賞)を発表した。幻想世界の〝街〟とスリリングな冒険活劇が並行して描かれ、この長編は世界中の読者を魅了した。村上春樹の〝街〟とは何か――『街とその不確かな壁』は、40年の歳月を経て、著者がその〝街〟に立ち戻り、新たに三部構成で描かれた長編小説である。文庫版は、上下二冊で刊行。 〜Amazonより〜
1980年の中編小説としてのこの本は読んだ記憶がないので、著者の「あとがき」を読んんで納得しました。回り回って、書き上げた作品だということが。
十七歳と十六歳の夏の夕暮れ、きみは川べりに腰を下ろし、〝街〟 について語り出す――それが物語の始まりだった。高い壁と望楼に囲まれた遥か遠くの謎めいた街。そこに“本当のきみ”がいるという。<古い夢>が並ぶ図書館、石造りの三つの橋、針のない時計台、金雀児(えにしだ)の葉、角笛と金色の獣たち。だが、その街では人々は影を持たない……村上春樹が封印してきた「物語」の扉が、いま開かれる。
〜上巻の帯より〜
彼の小説は、学生時代の恋愛が通底にある場合が多いです。今回の小説もそのパターンでした。壁のこちら側で文学をきっかけに知り合った【きみ】と【ぼく】。とてもいい雰囲気で二人の交際が描かれていきます。しかし、これから恋愛が進展しそうな時に隣町に住んでいた【きみ】は急に【ぼく】の前から姿を消します。二人で作り上げた不思議な物語を残して・・・・。
そして壁の向こう側の世界では【きみ】と【ぼく】は違った形で出会います。古い夢が並ぶ図書館。針のない時計台。高い壁に取り囲まれた世界には影がありません。その世界は、二人が作り上げた不思議な世界そのものでした。そのような感じで物語が進むので「ん?今どっちの世界だっけ?」と時折ページを戻って確認しがなら読み進めていきました。上巻は物語の展開が読めないので、ドキドキしながら読み進めました。
今までの村上春樹の作品と違い性的な表現は、抑えられている印象です。
それにしても、人生の中でお互いに最高の理解者であると思い、いろんなことを熱心に語り合うことができた【きみ】と出会えなくなった【ぼく】の喪失感が痛いほど伝わってくる描写でした。
喪失感を抱えた彼は、45歳の時に【穴】にストンと落ちてしまいます。彼女と作った物語の世界へと、影のない世界へと行きます。彼女と作った物語の世界の流れが再び1部の後半に描かれます。村上春樹のこの辺りの物語の繋ぎ方は本当にすごいなぁと思います。
さて、彼がこのまま影のない世界に残るか影と共に元の世界に戻るかの葛藤の場面は読み応えがありました。人間、誰しも自分に問いかけてどちらが正しいのか判断に迷う場面はありますからね。
元の世界に戻ったのは、【影】だったようなのですが・・・・。
上巻の後半から2部になります。元の世界に戻った主人公が、今いる仕事を辞めて新天地での生活が始まります。仕事先は図書館です。
図書館の奥まった半地下の館長室で、薪ストーブの火を見つめながら子易(こやす)老人は「私」に語りかける。「ここはなにより、失われた心を受け入れる特別な場所でなくてはならない」、と。そんなある日、「私」の前に不思議な少年があらわれる。「イエロー・サブマリン」の絵のついた緑色のヨット・パーカを着て、図書館のあらゆる本を読み尽くす高校生の少年だった。「その街に行かなくてはならない」――少年は自ら描いた〝街〟の地図を携え、「私」に問いかける。そして舞台は第二部の〝町〟から第三部の〝街〟へ。幻想と現世を往還する物語が、ふたたび動き出す……。
〜下巻の帯より〜
*なお巻末には、この作品の成立をめぐり、著者による「あとがき」が付されている。
2部では、福島県の会津若松の近くのZ※※町の図書館が舞台になります。元館長の子易さん、司書の添田さん、そしてヨットパーカーの少年。ブルーベリー・マフィンとコーヒーが美味しい『コーヒーショップ』という女店主との出会い。
彼が【何かと何かがつながっている】と感じ始め、物語が大きく動く動きます。
印象に残っているのは、図書館で元館長の子易さんと物語の進行に関わる重要な話をする場面です。その中の一つに子易さんが高校生の時に大切な彼女を失ってしまった彼に向かって「そう、あなたは人生のもっとも初期の段階において、あなたにとって最良の相手に巡り会われたのです。」という言葉が印象に残っています。最良の相手にいつ出会うかは、本当に人それぞれなのだと思います。
穏やかで心優しい子易さんとの彼の会話を軸に物語は最終段階へと進みます。
3部では、色々な謎が解き明かされていきます。
コーヒーショップの女店主がガブリエル・ガルシア=マルケスの『コレラの時 代の愛』の「亡霊」のことを彼に紹介する場面も印象的でした。この本も読んでみたくなりました。
死者との対話や魂といった抽象的なことが物語の大切な場面に挿入されていますが、考えてみれば、誰でも意識的あるいは無意識に死者との対話はしているのではないでしょうか。
さて、村上春樹の小説は、ハッピーエンドかバッドエンドか読者に委ねる終わり方をする作品が多いと記憶しています。
わたしは、この物語の最後はハッピーな方に解釈して読み終えました。
〜『あとがき】より〜
要するに、真実というのはひとつの定まった静止の中にではなく、不断のの移行=移動する相の中にある。それが物語というものの真髄ではあるまいか。僕はそのように考えているのだが。
『あとがき』にこの物語に込めた作者の思いが書かれています。『コロナ・ウィルス』が猛威を振い始めた2020年の3月に書き始め3年近くかけて完成させたそうです。作品に何らかの影響があったかもしれないといったことも書かれています。『高い壁』の描写が生々しかったですから。圧倒的な『壁』の存在を感じました。
自分の思いではなく、何かに導かれて生きていることを実感している自分にとっては、とても心の奥に響く物語でした。